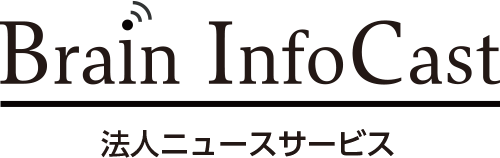米投資会社のベインキャピタルは、三菱ケミカルグループから買収した田辺三菱製薬について、外部からのライセンス導入への投資を拡大する。自社創薬に加え、M&A(買収・合併)や治験の早期段階から一定の開発リスクを取った新薬候補の導入にも資金を振り向け、パイプラインの拡充による企業価値向上を図る。 導入にあたっては、保有するライフサイエンスファンドでの投資目利き力やネットワークを活用し、田辺三菱の開発方針に合致するパイプラインの獲得を目指す。 中長期の成長戦略を年度内に固める方針だ。
三菱ケミカルグループからの株式譲渡が完了し、田辺三菱は7月からベイン傘下の製薬会社として新たなスタートを切った。 12月に社名を「田辺ファーマ」に変更する。 買収完了後、田辺三菱の投資担当者であるベインキャピタル・ジャパンの末包昌司氏と河本信太郎氏が取材に応じ、成長戦略を語った。
三菱ケミカルGは、本業の化学事業の収益力強化が課題となるなか、大規模投資を要する医薬品の研究開発が重荷となり、完全子会社化から5年で田辺三菱の切り離しを決めた。 売却額は約5100億円。 買収当初に企図していた化学と医薬のシナジーは希薄化したとして、田辺三菱の今後の成長のために資金力のある最適なパートナーが必要であると判断した。
末包氏は、三菱ケミカルG傘下で「医薬品事業への資源配分の優先度は高いものではなかった」と振り返る。 資金投入やリスクテイクが難しい状況であったならば「田辺三菱のポテンシャルを考慮すると最適な状態ではなかった可能性がある」と述べ、「今後はベインが一体となり田辺三菱にとって最適な戦略を採っていく」方針。 その手段の一つが導入やM&Aによる継続的なパイプラインの拡充だ。
ベインは田辺三菱が保有する「創薬から開発、製造、販売にいたるすべてのバリューチェーンでしっかりした力を持つ」(末包氏)点を評価する。 一方で、中長期的には自社創薬品が進展するが足元のパイプラインが十分ではないと指摘。 国内外からの導入に力を注ぎ、「M&Aが必要なら追加投資もいとわない」(同)。
従来の導入活動のほとんどは治験後期段階や上市ずみ製品が対象となっており、「これまでリスクの少ない導入が多かったが、一定のリスクを取って資金を投じていく」(河本氏)方針に転換する。 70社以上のバイオテックなどへの投資実績を持つ、ベインの米国ライフサイエンスファンドの目利き力とネットワークを活用しながら導入案件の獲得を加速する。
末包氏は、「より早期段階のパイプラインで田辺三菱のプラットフォームを活用できるものがある」と見込み、成功すれば「田辺三菱が得る収益が増え、それが次の導入やM&Aの原資になるといった良いサイクルが生まれる」と展望する。
ファンドの投資対象となる企業には、第2相臨床試験(P2)以降の比較的治験後期段階のパイプラインを有し、田辺三菱がカバーする代謝、免疫、神経、がん、ワクチンなどの疾患領域をターゲットとする企業が多く含まれる。 その約9割が日本への導出パートナーが決まっていないという。 河本氏は「このネットワークを生かして田辺三菱の導入活動を活発化していける」とにらむ。
案件によるが、ベインの投資期間は5年程度が目安となる。 河本氏は「パイプラインの充実が一番の企業価値向上につながる」といい、ピーク時売上高や十分な薬価が見込めるような開発候補品の拡充を図る。