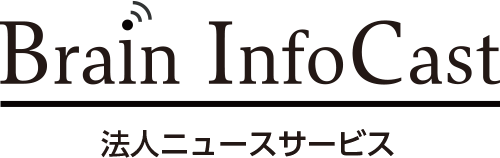江戸時代、大名は江戸と国元とを1年ごとに往復した。「参勤交代」と呼ばれる制度だ。 江戸での生活も含め多額の出費が必要で、大名の力をそぐ手段と言われたことも。 なぜ始まり大名行列の様子はどうだったのか。 行列を描いた絵巻や屏風(びょうぶ)が知られる加賀藩を中心に変遷と実像を探った。
石川県立歴史博物館は「加賀藩大名行列図屏風」を所蔵する。 藩主を中心に473人、馬14頭、駕籠(かご)4丁が登場する。 順番や服装、持ち物が一目で分かる作品だ。
「実はこの絵は江戸時代ではなく、1940年ごろに完成しました」と学芸員の中村真菜美さんが笑う。 確認されている加賀藩の大名行列を描く絵巻などのほとんどは明治以降、行列帳などを参考に時代考証して描かれた。 「江戸時代への懐古の念や、郷土史に対する関心の高まりの中、制作されたと考えられます」
領内では、前田利家の桶狭間の戦いからの凱旋(がいせん)を描く絵が幕末に流行する。 100万石まで出世し繁栄を築いた前田家、特に家祖利家への憧れが強かった。 明治に入っても続き、まちおこしのためもあって前田家にちなんだ祝祭の開催が盛んになる。
1891年に開かれた金沢開始三百年祭では、前田家の行列が練り物の演目となった。 「加賀藩の大名行列は大衆に親しまれ、大正後期以降は地元の画家が描いた絵巻が郷土史展覧会や書籍類に登場し、屏風にも描かれるようになります」
実際に参勤交代にかかった日数や予算は―。 多くは金沢から北国下街道、今の富山、新潟両県を経て長野県に入り中山道を通って東京に至る12泊13日のコースだった。
糸魚川宿で2千人分、1泊2食分の旅籠(はたご)賃が銭で約390貫という記録がある。 学芸員の吉田朋生さんは「現代価値への換算は難しいが、一例として1千万円ほどです。 江戸までの12泊と、川渡しや宿場へのお礼、幕府への献上物の費用などを合わせると約1億5千万円になるのでは」。
江戸での滞在、屋敷の維持管理などの費用もかかる。 藩財政への影響の分析は難しいが「藩や藩士にとって大きな負担だったのは確かです」。 /インタビュー/石川県立歴史博物館学芸員/吉田朋生さん/見えで行列が長く?/簡易トイレ、漬物も運ぶ
〈いつ始まった?〉
加賀藩の場合、1600年の関ケ原の戦いの前から、前田利家の正室芳春院(まつ)が人質として江戸に在住しました。2年後に加賀前田家2代で、藩主の利長が母の見舞いのため江戸に行き、徳川秀忠にあいさつしたのが始まりです。
家康は戦いの後、外様大名が江戸に来ること、その妻子の江戸居住を推奨しました。 これもあって大名とその重臣が人質を江戸に置くことが習慣となり、将軍への忠誠を示そうと、毎年のように大名が江戸に来ました。
そこで34年に3代将軍家光が譜代大名の妻子も江戸に移すように命じ、翌年に新たな「武家諸法度」を発布、参勤交代が正式に始まりました。 全国の300諸侯が江戸に屋敷を構えました。
1862年に制度は事実上、廃止されました。 この227年間で加賀藩の参勤交代は約190回です。 藩主の体調が悪かったり、藩主の交代があったり、領内が飢饉(ききん)となったりしたときは幕府から免除されたためです。
〈参勤交代とは?〉
「参勤」とは江戸に上り将軍と謁見(えっけん)するために、「交代」で江戸に詰めるということです。江戸から国元に戻る際には、将軍の許しを得る必要がありました。
行列での従者の員数は1615年の武家諸法度で作法として「100万石以下20万石以上は20騎以下とし、10万石以下は家禄(かろく)に応じ」でした。 幕府はその後「従者の員数、近年甚だ多し」と、ふさわしい人数に減らすよう何回か求めています。
なので大名に出費させて勢力をそいだとは単純には言えないでしょう。 大名の石高や家の格に応じて持ち物や服装が変わってきます。 大名の競争意識をあおり、見えも働いたのでしょう。 それで行列は長くなりました。
人数を多く見せるため、今風に言えば専門の人材派遣会社もありました。 江戸に入るときなどには臨時に雇って水増しするという方法もあったようです。
〈加賀藩の実態は?〉
幕府の示す基準などから考えると、数百人で済む計算ですが、実際の記録を見ると人数は約2千人から4千人です。藩財政の窮乏に伴って、従者の人数を簡易にするよう家臣にお触れを出したこともありました。
1827年の前田家13代、斉泰の参勤では、直臣(藩の家臣)、陪臣(直臣が家禄(かろく)に応じて連れていく従者)、奉公人(藩の雇用者、足軽、小者)、宿ごとに雇う宿継(しゅくつぎ)人足など計2千人です。 奉公人には臨時のアルバイトも含まれます。
編成は、先頭が長柄、弓、筒の部隊の「御先三品」、次が「行列の内」とされる本隊と殿(しんがり)です。 本隊は藩主とその御供行列で藩主が所有する武具、道中道具、駕籠(かご)、替え馬となります。 殿は行列全体を統括する重臣らの部隊で、医者らも含まれます。
最後は「行列の外」と呼ばれ陪臣や奉公人です。 荷物運びに加え、川渡し場や難所の下見、関所での交通整理といった雑用もあります。
〈なぜ大人数に?〉
藩主と藩士の大移動です。大量の荷物が必要となります。 幕府は宿場の馬や人足が酷使されないように、運べる重さを馬は約150キロ、人は約20キロと制限していました。
武具だけでなく、雨に備えたかっぱ、果ては藩主の簡易トイレ、飲み水、酒、しょうゆ、重しを載せた漬物まで運びました。 藩主の駕籠を担ぐ人は通常よりも多く必要です。 馬を引く人も要ります。 人数はどうしても増えてしまいます。
出費の削減策として、古着の羽織着用の許可や、昼ご飯のコストを減らすため足軽らは宿場でつくった弁当持参というのもありました。 将軍への服属儀礼/江戸の流行地方へ伝達も
参勤交代は将軍への服属儀礼として始まった。 大名は通常は1年交代だが関東は半年で交代、水戸藩と老中など役付きの大名は江戸定府と細かく定められている。
大名の定期的な移動もあって、地方から人と金を集めた江戸は大消費都市に発展した。 浮世絵や食も含め多様な文化を生み出し、大名や家臣らが国元に戻る際には、流行を持ち帰り広める役割も担った。 江戸を中心として街道や宿場が整備され交通も発達した。 これがお伊勢参りなど庶民の旅行ブームにも役立った。
大名らは年貢米の販売のため経済の中心である大坂に蔵屋敷、幕府が西日本支配の拠点とした京都にも屋敷を置いていた。 幕府による政治と経済の分離が、現代の課題に即して言えば、過度な江戸一極集中を防いでいたとも言える。 (共同通信編集委員 諏訪雄三)
主な参考文献 「参勤交代道中記―加賀藩史料を読む―」(忠田敏男著)、「参勤交代」「『参勤交代』の不思議と謎」(山本博文著・監修)、「詳説日本史B」(山川出版社)