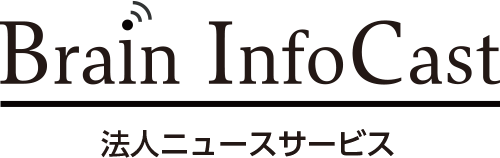おがわ・ようこ 1962年岡山市生まれ。早稲田大第1文学部卒。 88年に「揚羽蝶(あげはちょう)が壊れる時」でデビュー。 91年「妊娠カレンダー」で芥川賞。 代表作に「博士の愛した数式」「密(ひそ)やかな結晶」など。 2021年に紫綬褒章を受章し、菊池寛賞にも選ばれた。 兵庫県西宮市在住。
教育に新聞をどのように活用できるかを考える「第30回NIE全国大会」(日本新聞協会主催、神戸新聞社など主管)が7月31日〜8月1日、神戸市で開かれた。 スローガンは「時代を読み解き、いのちを守るNIE」で、約1800人の教育・新聞関係者が集まった。
1日目の全体会では、大会実行委員会の竹内弘明委員長が基調提案として、真偽不確かな情報が社会にあふれ、インターネット上の悪口や中傷で人の命が奪われることもあると指摘。 「正確な情報を取捨選択し活用する能力を身に付け、インターネットとうまく付き合うために、新聞やNIE活動は有効だ」と述べた。
パネル討議には、日本新聞協会NIEアドバイザーで兵庫県西宮市立浜脇中学校の渋谷仁崇主幹教諭らが参加した。 高校生だった1995年、阪神大震災で被災した渋谷教諭は、何もできずもどかしい思いをしたという。 そうした自身の経験をもとに、新聞を通じて防災や減災を考えてもらう授業を行ってきた。 「これからの災害に向け、生徒が自分事として考えられるよう取り組みたい」と話した。
司会を務めたジャーナリストの池上彰さんは「伝える側にとって一番大事なことは、情報を正確に早く伝えることだ」と強調。 その上で、記録だけでなく戦争や大災害を体験した人たちの記憶を次の世代に伝承するのは、地元の新聞の役目だと締めくくった。
記念講演では、作家の小川洋子さんが登壇し、交流サイト(SNS)の画面に表示される言葉は、相手が発した言葉の本当の意味を伝えてくれているとは限らないと述べた。 一方で、「情報は受け取った側の人間性や人格が問われる。 自分に関係ないとすぐに切り捨てるのではなく、受け取る側の心の余裕、包容力をぜひ若い人に育ててほしい」と訴え、「その力を養うには文学を勧めたい」と力を込めた。
2日目は公開授業や実践発表が行われ、熱心に意見が交わされた。 同級生同士が、自分が選んでスクラップした記事の意見交換をした結果、それぞれの興味や関心の対象が広がった、とする報告もあった。
来年の全国大会は広島市で開かれる予定。 小川洋子さん講演要旨
小川洋子さんの講演要旨は次の通り。
自分とは価値観が違う他者のことを想像し、言葉でつながれるのは、人間だけ。だからこそ想像力を育むことが重要だ。
例えば人間には、誰かが「死にたい」と言ったとしても、心の中では「死にたくない」と思っていることを感じ取る力がある。 交流サイト(SNS)は、小説や新聞と違い、言葉を文字通りにしか受け取れない。 言葉の向こう側を感じることができないと思う。
人間の心に届きやすいのは、五感に直接訴えかけてくる物だ。 紙の感触やインクのにおい…。 かつて「源氏物語」の時代は、文字を書こうとすれば墨をする運動から始まった。 デジタルの時代では、肉体が置いてけぼりにされている気がする。
今の自分が関心がない世界の方が何千倍も広く、それを知れば大事なことと出合えるかもしれない。 その意味で、さまざまな情報が視界に全部収まる新聞は魅力的だ。