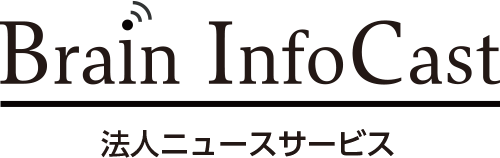中堅・中小企業に脱炭素への取り組みが広がっている。温室効果ガス(GHG)排出量の算定を終え、次のステップとして排出量の削減に進む中堅・中小企業が増えている。 だが、実際の削減となると課題も少なくない。 サプライヤーとの取り組みを始めたカナエ(大阪市中央区)、削減を継続的な活動にしようとするエイワ(長野県安曇野市)の2社を取材した。
■カナエ/サプライヤーと算定 社内データ活用手順確立
カナエは医薬品や化粧品、食品の包装材料の販売、国内3工場での受託包装加工を行っている。従業員は約520人。 取引先からの質問や要請を受け、GHG排出量の算定や目標の設定に着手した。 目標については、パリ協定達成に必要な削減水準を基準とする「サイエンス・ベースド・ターゲッツ(SBT)」の認定を目指した。
主に事業所を対象とするスコープ1、2の排出量は、ガスや電気の使用量から算定できる。 問題はスコープ3の排出量だった。 スコープ3は調達した原材料など、あらゆる排出が対象となる。 仕入れなどの社内データを算定に活用できるように整理する作業に労力を費やした。 担当したCSR推進課の大森寛之課長は「算定手順を確立できたので、次回からは負担を軽減できる」と見通す。
2030年度までにスコープ1と2の排出量を23年度比42%削減、スコープ3の排出量を25%削減する目標を設定して24年8月、国際組織からSBTとして認められた。
削減においてもスコープ3は難題となる。 スコープ1と2は自助努力で減らせる部分が多く、2工場では再生可能エネルギー由来電力の購入も始めている。 対してスコープ3はサプライヤーの協力が不可欠。 環境省の24年度「バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業」にサプライヤー2社と応募し、採択された。
2社はともに中小企業であり、排出量の算定は初めて。 カナエは算定の狙いを説明し、必要なデータを入力するエクセルシートを作成して2社に渡した。 スコープ3で苦労した経験を生かし、入力項目を絞る工夫をした。 疑問点があれば、環境省が委託したコンサルティング会社に相談して算定を支援した。
カナエは今回の知見を生かし、もう1社とも算定を計画している。 今後もSBT達成に向けて活動する。 「いずれは排出削減が評価され、取引の拡大につながると期待している」(大森課長)。 また「本業とのつながり」も意識する。 排出量の削減実績を現場での省エネルギーやカイゼン活動の成果と連動させ、全社で一体感を持った脱炭素活動へと進化させる方針だ。
■エイワ/菓子業界の先導役に 環境貢献を定量化・発信
「二酸化炭素(CO2)を算出できないか」。小高愛二郎会長からの問いかけがきっかけだった。
エイワはマシュマロを主力とする菓子メーカー。 従業員は約140人。 小高会長は全日本菓子工業協同組合連合会など業界団体の理事長を務めており、脱炭素の取り組みを業界全体に広げたいとの思いがあった。 他社に賛同してもらうためにも、まずは自社が実践したいと考えた。
これまでに重油からガスへの燃料転換、照明の発光ダイオード(LED)化、太陽光パネルの設置を進めてきた。 今井一馬副社長は「環境に貢献する取り組みをやってきたが“点”の活動だった。 『良いことをしているんだろうな』と思っていたが、定量化して伝えられていなかった」と課題を感じていた。 排出量の削減効果が分かれば、環境貢献を発信しやすくなる。
製造に使うガスを購入している岩谷産業に相談し、23年にゼロボード(東京都港区)のGHG算定システムを導入した。 さらに24年、環境改善を経営と一体化する国際規格「ISO14001」を取得した。 GHGの算定後、排出削減を継続的な活動にする社内体制を整えるためだ。 「点の活動が面となり、立体となって継続的に改善することが大事」(今井副社長)と説明する。
ただ、「算定結果をどう評価して良いのか分からなかった」(同)。 そこで同業者の公開データを調べ、1億円を売り上げるために排出したCO2排出量(原単位)を比較し、現状を把握することができた。
原単位を前年度比2%以下にする目標を設定した。 課題は実際の削減だ。 すでにLEDや太陽光パネルを導入しており、次の施策が思い当たらない。 スコープ3も「サプライヤーにどのように協力してもらえば良いのか」と悩む。 排出量を抑えて生産した原料の調達など「できることを話し合っている」(同)段階だ。
外部発信も課題だ。 「従業員が取引先にエイワの環境活動を説明できるようになったら、商売の深みも変わってくる」と期待する。
■脱炭素経営、今から準備 「コストよりCO2へ」
カナエ、エイワともGHG排出量算定後の課題として、スコープ3の排出量削減を挙げた。 2社に限らず、削減にはサプライヤーの協力が不可欠。 まずは排出量の算定を依頼する必要があるが、サプライヤーにとって負担となる。
他にも課題がある。 カナエは算定を支援した2社からは「脱炭素に取り組むスタートラインに立てた」というコメントをもらえた一方で、「自社の排出量が多いのか、少ないのか分からない」との感想も聞いた。 算定結果の評価も、サプライヤーと脱炭素を推進する課題となりそうだ。
実際の削減に取り組んでもらうこともハードルとなる。 省エネ設備の導入はコスト低減につながるので経営メリットとなるが、初期投資を考えるとためらう。
こうした課題がありながらも、中堅・中小企業に算定や削減を求めるプレッシャーが強まっている。 プライム市場上場の一部の大企業は27年3月期から、スコープ3を含めた排出量の開示が義務化される。 排出量算定の国際基準「GHGプロトコル」のワーキンググループメンバーである待場智雄氏(ゼロボード総研所長)は、「初めは大まかな情報で良いかもしれないが、精密な排出量が求められるようになれば、より多くのサプライヤーが算定を求められそうだ」と予測する。
また、今は取引でCO2削減よりもコストが重視されているが、待場氏は「CO2が財務会計のように経営や生産の効率化、良い商品を作るための要素となる世界が来ると予想している」(同)と話す。
大きな潮流として脱炭素の方向に向かっていることは確か。 中堅・中小企業も脱炭素経営に移行する準備が求められる。 政府や産業界は、算定の負担軽減や排出削減のインセンティブを考える必要がありそうだ。