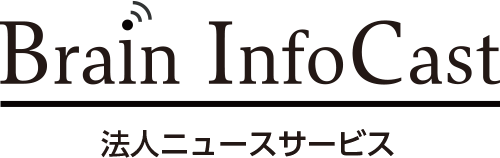家計の支出に占める食費の割合「エンゲル係数」が、歴史的な高水準に達していることが1日、共同通信の分析で判明した。総務省が公表する「家計調査」のデータを使い、道府県庁所在地と東京都区部の全国47都市の過去40年にわたる係数を5年ごとに平均化すると、直近の2020〜24年に37都市で最高値を更新した。 47都市でトップは大阪市で31・2%。 最も低かったのは水戸市の24・9%だった。 全国平均は27・5%。 近年の食品の値上げラッシュが生活の重荷になっている現状が浮き彫りになった。
25年は半年分しか公表されていないが、コメの値上がりが響き、エンゲル係数は高止まりしている。 他の食品も高騰が続いており、今後も高い水準で推移しそうだ。 一方、データからは食生活が変わっていく様子もうかがえた。
分析では、2人以上世帯の数値を用いた。 比較できる1985年以降を対象に検証。 政府は毎月と単年の数値を発表しているが、短期間の数値ではばらつきも大きいため、5年ごとの係数を独自に算出、都市別の長期的な推移を明らかにした。
生活に欠かせない食費の負担が重くなれば、他に支出を回せなくなるため、エンゲル係数は暮らし向きを示す指標とされている。
全国平均は下落基調が続いてきた。 85〜89年が26・1%で、その後25年間は23〜24%台だった。 だが15〜19年に25・6%へと上昇し、20〜24年に27・5%に達した。 20年ごろは新型コロナウイルス禍で外出関連の消費が落ち込み、相対的に食費の割合が高まった。 その後は円安進行や原材料高などを受けて食品の値上げが本格化した。
20〜24年に最高を更新した37都市のうち、大阪の次にエンゲル係数が高いのは青森市(29・6%)で、神戸市(29・2%)が続いた。
直近の5年で最高値を更新しなかった10都市のうち9都市は85〜89年、1都市は15〜19年がそれぞれ最高だったが、それらの都市のほとんどが20〜24年も最高に近い値だった。