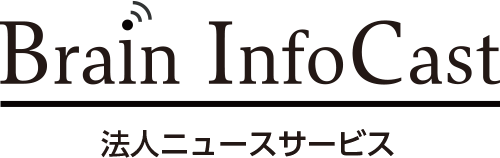三洋化成は、国内外の全生産拠点を対象とした設備の集約化に乗り出す。樋口章憲社長をオーナーとする「生産設備改革プロジェクト」を今年度から立ち上げ、市場環境に合った生産体制や全体最適化で設備稼働率を向上させ利益体質へ改善を目指す。 5カ年計画を想定し2030年度にめどを付ける。 並行して自動化・機械化設備の導入やオペレーターをはじめとした従業員のリスキリング(学び直し)制度も構想。 設備集約化による利益改善効果と自動化をはじめとした設備投資費用も発生するが、30年以降の経営環境を見据えた長期視点で実行していく。
三洋化成グループの生産拠点は国内5工場、海外3工場(米国、韓国、タイ)体制。 25年度を最終とする現中期経営計画ではサプライチェーン改革を推進し、ソフト面の取り組みでは研究出身者を集めた部門「ものづくり革新センター」を23年度に発足。 研究員が生産現場に足を運びオペレーターらと意思疎通することで課題を抽出、生産プロセスを見直すなどの効率化を推進している。 一連の活動は「ものづくり改革プロジェクト」と呼び、25年度には22年度比で約30億円の営業利益改善を見込んでいる。
一方、反応設備などハード面の改革では、今年度から社長直轄の生産設備改革プロジェクトを始動させた。 同社は機能化学品の多品種少量生産を強みに成長を図ってきたがプロジェクトの方向性としては、供給数量を維持したまま設備の稼働率を上げていく考え。 生産効率を向上させ、老朽化した設備は休止することで修繕費も抑制できる。
国内外の工場で生産最適化を進めていくなか、製品によっては生産拠点が変わる可能性もあるものの、営業部門をはじめ他部署とのコミュニケーションを密に行い、集約化できるものから実行に移す。 マザー工場である名古屋工場(愛知県東海市)では有機合成プラントで一部、着手した。
設備の集約と並行し進める自動化は、危険な接触がともなう業務など安全に関わる作業の置き換えを最優先する。 集約化と自動化で将来的には少人数でのオペレーションを想定するが、従業員は雇用を前提としリスキリングの機会などを設けることで、活躍できるフィールドをより広げてもらう考え。 また休止したプラントの一部は、安全教育やスキル向上などを目的とした教育施設としての活用も検討している。
生産設備改革プロジェクトのプロジェクトリーダーを務める白波瀬直孝氏は「設備集約化は三洋化成の未来につながるアクション。 現在は生産や営業部門も含めて集約化できる製品、できない製品などを議論している。 プロジェクトは30年度の完了を目指しているが、集約後の仕組みを効果的に継続できる体制もさまざまなメンバーとすり合わせしている」と話す。
同プロジェクトにおける利益改善効果や自動化をはじめとした設備投資額などの数値は、26年度に始動する次期中計で公表するとみられる。