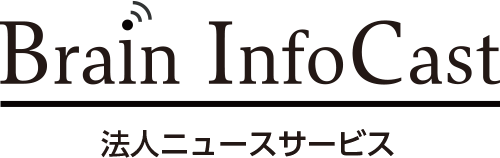バイオ関連事業を中核領域と位置づけ育成を図っている長瀬産業。2023年には子会社のナガセヴィータ(旧林原)にナガセケムテックスの生化学品事業を承継し、グループのバイオ技術を結集した。 微生物の探索・設計などの代謝工学や遺伝子工学、発酵生産物や酵素反応物製造を強みに、新たな成長のステージを目指している。 4月1日付で、中軸を担うナガセヴィータの社長に就任した万代隆彦氏に舵取りの方針を聞いた。
■…入社以来、技術畑を歩んできました。
「生産や技術のことはわかるが、営業の経験がなく、経営の舵取りができるか不安もあった。 だが親会社の長瀬から一緒に進んでいこうと声をかけられ、背中を押してもらった。 会社のこれからの体制などを考えたときに、いま私にできることをやらせてもらおうと決心してお受けした」
■…就任に際して社内に3つのメッセージを発しました。
「昨年の社名変更とともに企業として目指す姿、重要視する価値観を定めたパーパス(存在意義)とバリュー(行動指針)を掲げており、一つ目はこれらをすべての活動の基軸としようということだ。 新たな挑戦を恐れず、自ら行動し、誰に対しても誠実であって欲しい。 もう一つは業務品質の向上。 生産性はもちろん、個々人が自らの仕事をもう一度見直し、本当に顧客が求めているアウトプットを実現できているか考えることが重要だ。 最後は笑顔でいること。 失敗しても下を向かずに笑っていれば、周囲が声をかけて励ましてくれるものだ」
■…グループが強みとするバイオ技術の中核を担います。
「われわれは、微生物を活用した糖製品製造技術に強みを持ち、新規酵素の探索技術やそれら酵素を用いた酵素反応による物質変換技術をもつ。 食品向けの産業用酵素を生産するナガセケムテックスの生化学事業が統合され、酵素の発見から製品化、さらにはアプリケーション開発そして販売まで一貫して手掛けることになる。 長瀬産業は昨年、旭化成ファーマから診断薬や診断薬酵素事業を買収しており、同社の高感度な診断薬酵素の研究開発力と、われわれが培ってきた酵素や酵素反応物の研究開発能力を組み合わせれば、さらなる事業拡大が期待できる」
■…5カ年の中期経営計画は最終年度を迎えています。
「コロナ禍や社名変更、生化学品事業の統合など大きな環境変化に見舞われた期間となった。 主原料のでんぷんやユーティリティの高騰も経営に大きな影響を与えた。 サステナビリティの取り組みでいえば、わが社は岡山市が排出する二酸化炭素(CO2)量の約1%を占めており、積極的な情報開示で企業価値向上に努め、仏エコバディス社のサステナビリティ評価では最高位の『プラチナ』を2年連続で獲得できた」
■…来期から始動する次期中計の策定に入ります。
「『ワンNAGASE』の下、グループの一員として成長に寄与することは当然だが、個社としても成長曲線を描くためには、トレハロースやビタミンC誘導体『AA2G』などの主力製品の高付加価値化に加え、新製品の成長が欠かせない。 でんぷんに酵素を作用させて作る水溶性食物繊維素材『ファイバリクサ』や液状の『テトラリング』をはじめ、22年に上市した柑橘由来の味質改善素材『ナリンビッド』なども酎ハイやノンアルコール炭酸飲料などのニーズをつかんで引き合いが強い。 食品素材に加えて、酵素が工場の排水処理に用いられるなど今後も新たな提案を進めていきたい」
(聞き手=但田洋平)
<略歴>
〔まんだい・たかひこ〕1984年岡山大学農学部卒、林原入社。88年3月林原生物化学研究所天瀬研究所配属、2017年執行役員、19年取締役生産統括部長、23年常務取締役、25年4月ナガセヴィータ社長就任。 岡山県出身、64歳。
<横顔>
長瀬産業の完全子会社になって以降、ナガセヴィータ出身の社長は初めて。技術の知見や工場長としての経験も生かし、グループ融合や新事業開発での舵取りが期待される。 酒は飲むのに加え収集するのも趣味の一つ。 最近はウイスキーをコレクションし、ホームパーティーで客人に振る舞う。 ボランティアで30年以上、消防団にも参加するなど地元でも有名人だ。