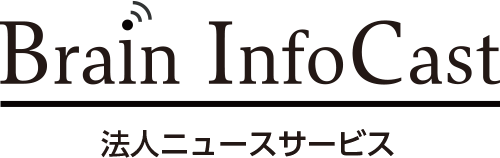バイオ医薬品の需要の高まりを追い風に、富士フイルムはバイオ医薬品の開発・製造受託(CDMO)事業が拡大する。モダリティー(治療手段)の多様化や複雑化が進む中、CDMOは製薬企業のニーズに応じた技術開発や生産能力の拡大に力を入れる。 製薬産業における米国の関税策の影響や事業環境、さらに今後の成長戦略について富士フイルムの飯田年久取締役に聞いた。
―CDMOの事業環境は。
「バイオ医薬品の大型薬(ブロックバスター)が出てきており、CDMOの需要の伸びは継続する。 米国での大きな需要の根底には供給能力の地域格差がある。 人件費といったコスト面から、バイオ医薬品の製造拠点は欧州に構えて米国に輸出する方が理にかなっており、国際分業が進んだ。 しかし医薬品の最大市場の米国でバイオ医薬品の供給力不足が進み、需要に近い地域で製造するということから米国のCDMOの需要は高まった。 米国の関税策は特殊要因として影響は考えられるが、需要を押し上げるというよりは米国内の製造能力を強化する計画の時間軸を縮める方向に働いた」
―製薬企業が米国内の自社設備の強化を進める中、CDMOに求められることは。
「供給能力があることは大前提だが、選ばれる上では品質とコスト、時間が重要だ。 製造の成功率が高く納期通りに製造できることが重視される。 富士フイルムのCDMOはデンマーク拠点において成功率が98%と高く、安定供給の実績がある。 さらに工場の設備を共通化することで製造技術などを拠点間で迅速に横展開する『KojoX(コージョーエックス)』により、米国拠点でも同様に製造が可能だ。 実績と高い信頼から、2028年度に稼働予定の米国拠点ではすでに培養槽4基で製薬企業との契約に至っている」
―日本国内の拠点の狙いは。
「27年稼働予定の国内初となる富山拠点は、日系の製薬企業からの期待が高い。 子会社の富士フイルム富山化学には低分子薬の製造ノウハウがある。 バイオの知見と組み合わせ、抗体薬物複合体(ADC)や、次世代抗体などの製造にも対応していく。 また治験薬から商用までをカバーできる設備を持つため、顧客となる製薬企業の幅広いニーズに応えることが可能だ」
―技術的な向上は。
「AI(人工知能)の活用の幅を広げていく。 培地製造を手がけル米子会社のフジフイルムバイオサイエンシズは、細胞の培養に最適な培地の開発にAIを使う検証を進めている。 最適な培地の効率的な開発から富士フイルムが支援することで、CDMO事業へのシナジーが期待できる」
【記者の目/技術の差別化で競争力に磨き】
製薬企業のバイオ医薬品のパイプライン(開発品一覧)は拡大傾向にあり、CDMOの需要も高まる。 飯田取締役は富士フイルムの競争力について、「品質や生産性を決めるのは細胞と培地とプロセスが重要。 富士フイルムにはその三つに強みがある」と強調する。 技術の差別化でニーズを取り込み、成長につなげる。(安川結野)