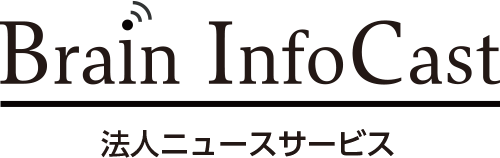北陸経済圏を管掌する経済産業省中部経済産業局の電力・ガス事業北陸支局が8月に公表した最新の北陸地域総合経済動向(2025年6月指標を中心として)によれば、生産は一進一退のなか、弱い動きを見せているものの、圏内の個人消費に改善傾向がみられるほか、公共投資が14カ月連続で前年を上回る伸びを見せており、中小から大規模な社会インフラプロジェクトが着実に進展していることがうかがえる。また、特筆すべきは北陸地域の全産業、製造業・非製造業の双方において、前年度を上回る計画が動向調査で明らかになっており、民間企業を中心に高い設備投資意欲が持続している。 これを裏付けるように雇用にかかわる新規の求人数は、この地域全体で2か月ぶりに前年を上回っており、北陸も全国的な人手不足課題に見舞われながらも、活発な企業の事業や投資意欲は強まっている方向だ。
<化学工業 後発薬が堅調、復調に期待>
<繊維工業 アジア・欧米向け引き合い>
北陸地域の鉱工業生産動向指数(6月速報)によると、医薬品や医薬中間体の比率が多い化学工業(医薬品)、各種の生産用機械工業(金属加工機械)などが一時的に減少しており、これらの影響から前月比3・0%減と3か月ぶりに低下を示した。
主要産業の業種動向からみると、北陸地域の化学工業は、現在、一時的には低下しているものの、後発医薬品の需要が現在も堅調に推移していることなどを背景に、実質的には横ばい傾向となっており、これからの復調も期待されている。 また、電子部品やデバイス関連工業は、主力のスマートフォン向けや自動車向けが振るわず後退の動きを示した。 ただ、自動車生産は、この地域と密接につながっている中部経済圏が今秋以降、大手自動車企業を中心とする自動車産業チェーンが、自動車生産の回復へ向かう動きもあるため、今後の動向に注目が集まっている。 一方、生産用機械工業は、海外向けを中心に堅調に推移しており「全体でみれば持ち直しの動きがみられる」(電力・ガス事業北陸支局)。 金属製品工業については、地域の主要産業であるアルミニウムサッシなどを中心に振るわず弱い動き。 ただ、伝統産業でもある繊維工業は、アジアや欧米など海外向けが引き続き堅調に推移しており、下げ止まり判断を示しており、これからの域内景況にかかわり判断上方修正の場面も出てきそうだ。
同様に財務省北陸財務局が6月に公表した北陸経済調査によると、財務局管内動向として、個人消費の緩やかな拡大と同時に化学工業も緩やかな回復途上にあるとした。 また個人消費動向では、5月時点の北陸における新車販売台数が前年を上回る伸びをみせており、新型車や低燃費車を中心に北陸圏内で受注や販売増が続くと見込まれている。 化学工業については、医薬品を中心として緩やかな回復に向かっていると判断、特に同局が実施した企業へのヒアリング調査では、ジェネリック医薬品を中心に供給増が続いており北陸エリアに立地する各社の工場は現在もフル稼働にあるという。 また、主だった企業は新工場や能力増強などの設備投資意欲もおう盛であり、こうしたことから生産規模の拡大と同時に全体景況へも好インパクトを与えていくとみられている。
<新幹線 敦賀−新大阪間の開通訴え>
「北陸はひとつ」「スマートリージョン北陸」を目指す未来ビジョンを掲げる北陸経済連合会(金井豊会長・北陸電力代表取締役会長)は8月初頭、総合対策委員会の主要活動として内閣府、国土交通省、文部科学省の関係省庁をはじめ、政府与党議員らを代表団が相次ぎ訪問、「政府に対する北陸経済界からの要望」をまとめ手渡した。重点要望項目として3点を示し、1令和6年能登半島地震・奥能登豪雨からの復旧・復興、2北陸新幹線の大阪までの早期全線開業、3「地方創生2・0」に向けたGX・DX推進を改めて各所へ要望した。 特に社会的にも注目が高い北陸新幹線の延伸については、敦賀・新大阪間の1日も早い認可と着工実現へ、駅位置やルートの決定、着工条件の早期解決と理解促進、環境アセスメントの迅速な実施などを強く要望。 これらに先立ち福井商工会議所は、初めて北陸新幹線をメインテーマとして7月、大阪商工会議所と意見交換会も実施しており、関西経済との密接な連携と相互の発展に向けて同新幹線は重要なカギを握っていることを双方で再確認した。
<水素・アンモニア供給網 産官学連携の強化など必須>
また、北陸地域の生産性向上と成長に向けた支援として、電力の安定供給にかかわる国の後押し、サーキュラーエコノミーに資する循環経済への移行加速化パッケージの着実な推進に向けた補助金拡充など諸制度の一層の充実化、そして地域の実情に即した水素・アンモニアの利用拡大にかかわる供給基盤整備事業の制度継続と拡大も訴えた。とくに水素・アンモニア供給チェーンは、前述の敦賀港を中心に北陸全域の経済規模と近隣他府県ともつながる重要な経済・社会基盤チェーンとしてとらえられているほか、産官学連携のさらなる強化や企業の成長力強化に向けた諸制度、環境整備もさらに必要とした。