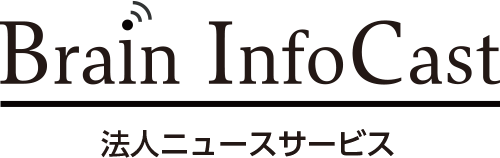帝人ファーマは27日、よだれが意図せず慢性的にあふれ出る症状である「慢性流涎(まんせいりゅうぜん)」についてメディアセミナーを開催した。疾患に対する認知度が高まらず、医療従事者の関心も低いなか、識者を招いて具体的な症状や患者が抱える課題を紹介した。 同社は6月にA型ボツリヌス毒素製剤「ゼオマイン筋注用」において、慢性流涎を効能または効果とする追加承認を取得しており、種田正樹社長は「身体的、心理的、社会的にも負担のある疾患だが、ゼオマインで患者のQOL向上に貢献していきたい」と述べた。
唾液には消化を助け、口のなかを清潔に保ち、食べ物を飲み込みやすくするといった働きがある。 1日の唾液の分泌量は1〜1・5リットルで、通常は無意識に飲み込んでいるが、慢性流涎はよだれが口腔から流れ出てしまう疾患。 主な原因としてパーキンソン病や非定型パーキンソニズム、脳卒中、脳損傷、脳性麻痺、筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィーなどの神経系疾患が知られている。
順天堂大学医学部神経学講座の服部信孝特任教授は、慢性流涎の困りごとと国内初の治療薬のテーマで講演。 患者や家族の日常生活に大きな影響を与えているものの、「医療従事者に相談できず、医療従事者の関心も高くない実態がある」とし、積極的な患者への声がけや治療の必要性を説いた。
ゼオマインは、帝人ファーマが2017年に日本国内における共同開発・独占販売権をメルツ社から取得し、20年に上肢痙縮の効能または効果で製造販売承認を得て販売を開始した。 21年に下肢痙縮の効能または効果の追加承認を取得し、さらに帝人ファーマが実施した日本国内第3相臨床試験(P3)およびメルツが実施した海外P3の成績に基づき、3番目の効能または効果となる慢性流涎の承認を6月に取得していた。