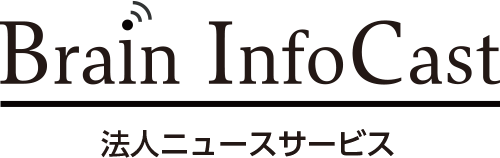城内実科学技術政策担当大臣は閣議後会見で、「日本の研究力」の現状に言及した。被引用数が多く質の高い論文とされる「Top10%補正論文」では「2年前の前回調査と同様の13位にとどまるなど、わが国の研究水準の相対的な立ち位置が改善されていない」と危機感を示した。 政府は現在、来年度から始動する国の「第7期科学技術・イノベーション基本計画」策定議論を進める。 次期基本計画に盛り込むべき、「日本の研究力(学術研究力と技術開発力)の強化策」については学術的には「大学のガバナンス改革や科学技術人材確保、研究の国際化」、産業的には「重要技術領域の特定を通じた研究開発投資の促進」などが重要になるとした。
ただ、「明るい兆し」もあるとする。 その一つが博士課程に進む学生数が増えていること。 「2年連続の増加であり、2024年度は前年度比4・9%増となった」とした。 さらに日本の大学による民間企業などとの共同研究で、「受け入れ額の継続的な増加」や日本の研究開発費が「緩やかではあるものの増加傾向にある」ことも好材料として挙げた。
これは文部科学省の科学技術・学術政策研究所(NISTEP)が公表した最新の科学技術に関する2つの基礎資料「科学技術指標2025」と「科学研究のベンチマーキング2025」を踏まえた発言。 論文数や質を国際指標とする「学術研究力」では国際ポジションの浮上の兆候はみえない。 この閉塞感を打破するには「日本の研究環境、研究資金、人材といった観点から改善すべき課題がある」との認識を示した。
企業研究者が重要な役割を担う国際特許指標(パテントファミリ)に焦点を合わせた「技術開発力」では、日本が20年にわたって「継続して世界第1位にある」と強調するが、「世界シェアは低下傾向にあり、中国がシェアを急激に拡大しており、今後も注視していく必要がある」と述べた。
なお、次期基本計画で選定する「重要技術領域」は「30年代を見据えてわが国が戦略的に取り組むべき重要な領域」であり、「社会経済上の影響などの観点を踏まえつつ、検討をいただいている」。 選定にあたっては「経済安全保障推進法に基づき示されている領域や個別に策定してきた分野ごとの(マテリアルをはじめとする)国家戦略」、さらには「科学技術外交を積極的に進めている分野などとも整合性が図られるものと考えている」と語った。