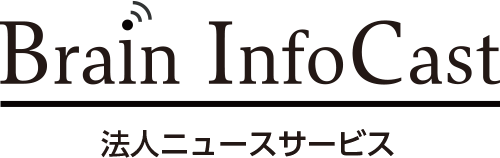米国研究製薬工業協会(PhRMA)とブリストル・マイヤーズ スクイブ(BMS)は28日、「革新的な再生医療等製品の持続可能なエコシステムの確立に向けて」のテーマでセミナーを共催した。産官学の意見交換を狙いとしたもので、冒頭にあいさつしたPhRMAのハンス・クレム日本代表は「日本における再生医療等製品をめぐる課題や機会、日本経済への成長の寄与に対して議論したい」と述べた。
仁木博文厚生労働副大臣は再生医療産業を取り巻く現状について触れ、今後の課題として(1)高額な治療や先進的医薬品に対する薬価のあり方(2)医療DXを用いた長期的な有効性と安全性の検証(3)標準治療に向けた適用疾病の拡大や製造コスト−を掲げた。
日本総合研究所の木下輝彦専務は、再生医療等製品の持続可能なエコシステムの確立に向け7月にまとめた提言書について紹介し、「価格制度・診療報酬制度の変革」と「課題の俯瞰と次世代のサイクル回転に繋がる施策の継続」の2項目で改革の必要性を説いた。
北海道大学大学院医学研究院血液内科の豊嶋崇徳教授は、キメラ抗原受容体遺伝子改変T細胞(CAR−T細胞)療法は画期的な医療手段だが、「さまざまな矛盾点が噴き出している」と指摘。 実施する病院が赤字になるなど医療者の自己犠牲の下で成り立っている事例を紹介し、持続可能な治療提供体制の構築の必要性を強調した。
包括的なエコシステムの構築や持続的発展に向けたパネルディスカッションも開催した。 再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)の畠賢一郎代表理事会長は、「製品のエコシステムは比較的うまく立ち上がっているが、医療全体のエコシステムがまだまだ不十分だ」とし、医療エコシステムの構築と開発・製造受託機関(CDMO)を中心とした製品の作り込みのバランスの重要性を強調した。